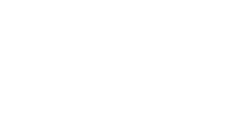同期の堀からバトンを受けました、3年で副務とスポンサー営業長をしております、伊藤と申します。私は「人間関係における相対性理論」という、車内の会話でも、同期内での仕事の割り振りでも、「相対的に見て一番できる自分がやらなければいけないな」と感じた人が主体的に動く、という経験則のことをよく考えます。「頼れる」という紹介は嬉しいものですが、私がこの代にいなかったとしても、相対的に見て2番手の人が代わりにやっていただけのことでしょう。そんなものです。
さて、暗い書き出しになってしまいましたが、10月の代替わりでは主務を引き継ぐほか、スポンサー営業長も続投する予定です。部の環境を内からも外からも働きかけて改善していく立場ということで、身の引き締まる思いでいっぱいです。身を尽くせればと思っております。
少し明るい話から始めさせていただくと、私は尊敬している人を聞かれたら、真っ先に答える2人がいます。母方の祖父母です。こういう類の質問に対して身内を挙げられるということをとても幸せに感じています。
祖母は専業主婦で、20年ほど前に社会的弱者を救済するNPO法人を設立し、今でも「仕事があることが幸せ」と言って活動しています。祖父は大学を学士で卒業するとそのまま理系就職し、定年退職してから修士をスキップして博士課程に進学、一昨年に82歳にして工学の博士号を取得しました。「今が一番幸せ」と言いながら研究室に通い詰めていた祖父の背中は、当時中学・高校生だった私にはとても格好良く写りました。「今が」という言葉の真意を聞こうと思ったことはありませんが、家族のためにずっと生きてきた祖父が、70歳後半にして自分のやりたいことに取り組めたというのが幸せそのものだったのだろうと推察しています。そして何よりも、話し上手で行動力のある祖母と、寡黙で理論派の祖父のコンビは完璧に感じます。2人よりも理想的な夫婦関係を目の当たりにすることは今後ないだろうと確信できるほどです。徒歩10分でそんな素晴らしい祖父母に会える最高の場所に私は住んでいるわけで、埼玉もまだまだ捨てたものではないのでしょう。
それでも現状の自己に対するジレンマというのは常に付き纏います。役職や普段の連絡の様子を見て私を「規律のしっかりした人間」と勘違いする人が多いですが、そんなことはないと思っています。部活の連絡は迅速ですが、大学の課題はいつだって期限ギリギリに仕上げて提出しますし、部室の片付けは積極的にやるくせに自室は全く片付けないためひどく散らかっています。仕事が多いのは好きでやっているのである程度受け入れられますが、その姿勢が自分のための努力に反映されていないことには、自分自身が一番疑問に感じています。
ゴルフ部においては、ベストスコアを更新した11月ごろから約半年間、スコアがなかなか伸びないことに悩まされました。たくさん働いた上で練習量も確保したつもりでいましたが、肝心のゴルフが伸び悩んだために凄まじい自己嫌悪に陥るわけです。好きで働いておきながら勝手なことを言うなとは自分でも思いますが、それにしてもこの類の感情から逃れられる日は来るのでしょうか?
悠長なことは言っていられません。現状を打破するために今考えているのは、「間の理論をすっ飛ばす」ということでしょうか。あらゆる身体感覚/活動とその結果の間には、必ず理論が介在すると思っています。
趣味の1つであるクラシック音楽を例にとると、私は初見の曲を聴けば大方どの時代の誰が作曲したものか推察できます。特にショパンの次に好きな作曲家であるクロード・ドビュッシーは明確で、特有の輪郭の曖昧さと構成から間違えることはないと信じています(余談ですが、幼少期に母親の演奏する『アラベスク 第1番』を聴き続けた影響で、音楽の原風景の1つとなっています)
専門的な音楽教育は受けておらず、調性の初歩で挫折した私であっても、感覚的にわかるわけです。音楽理論的に言えば、多用する和音の種類、進行の方法などの根拠を持つことはできるのだと思いますが、圧倒的な鑑賞量がそれを不要とします。
同様のことはゴルフでも感じます。例えばアプローチの際に、インパクト前後で手元を止める意識で打つと出球が高くなります。これは、ハンドレイトな状態でインパクトすることによってロフトが寝るために打ち出しが高くなる、という理屈を挟むことができます。この因果関係は試行錯誤の中で発見し得るものですが、前もって理論を知っておけば、身体感覚の定着のみに集中することができるわけです。このような類似性は2つに限った話ではなく、色んなところで見られるのでしょう。
大学で初心者としてゴルフを始め、3年半で結果を出すことが求められる多くの部員にとって、身体感覚と結果を介在する「理論」をたくさん知っておくことは重要であるように思います。その上で頭でっかちになることなく多大な練習量を確保することで、結果を残すゴルファーになれるのでしょう。私は部内の誰にも負けないくらい理論を吸収してきた自負はありますが、それを身体感覚レベルで染み込ませられるほどの練習力は確保できていなかった、ということが推測できます。たくさん学ぶ、考える、それと同じくらい球を打つ、それに尽きるのでしょう。
頑張らなかったら更なる自己嫌悪が待っていると考えると、今までよりも一層身を尽くして自分のために努力する気持ちが湧き出てきます。その先に「仕事があって、さらに自分のために努力できている今が幸せ」という境地が待っているのでしょう。そう信じてやみません。
続いては私と同じ理学部の地学系の学科に進学しておきながら燃費の悪すぎるハイオク車に乗り続ける温室効果人間、佐藤雄士郎に引き継ぎたいと思います。