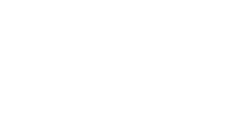伊藤からパスを受けました、3年の佐藤です。
男子春季リーグ戦が終わりました。
経験者として入部して以来リーグ戦で活躍したいという思いを持ちながら2年間伸び悩み、この春やっとのことで出場できたことは端的に嬉しく思います。満足いく結果とは到底言い難いものでしたが、この経験を最大限活かして今後の成長に繋げていきたいです。
またリーグ戦の4日前、朝練で肉離れを起こし試合に出られるか怪しい状態になってから2日間の試合を終えるまで、家族をはじめ同期、先輩、後輩、ゴルフコースや練習場の方々、(今回の僕の場合は病院の方々も…)などあらゆる人々の手助けのおかげで自分たちの活動が成り立っているのだということを改めて心から実感し、身の引き締まる思いです。
話は大きく変わりますが、僕はこれまで、現4年の守安さんと共にリーグ戦の写真撮影を担当してきました。今後のことを考えると現1/2年生で誰か写真撮影をやってくれる人がいるといいなー、、、と思っているところです。《もしやりたい人がいれば守安さんか僕に連絡をください!!》
ここからは、僕が思う(もしかしたら皆さんもなんとなく思っているかもしれないという期待とともに)写真についてのあれこれを、世の中の需要など気にせずに、徒然なるままにそこはかとなく言葉にしてみようと思います。この文章に最後までお付き合いいただける奇異な方は果たしていらっしゃるのでしょうか??(伊藤伶は確実に読んでくれます。よね。)
<写真の特殊さ>
少し周りに目をやると、世の中には写真が溢れています。インスタの映え写真、昔の家族写真、広告に使われている俳優の写真、図鑑に載っている昆虫や植物の写真、トランプが演説する写真、大谷翔平がホームランを打つ写真、文春砲のスキャンダル写真、岩合光昭が撮った猫の写真、抽象画のような芸術写真。
現在、ものを表現する方法は写真以外にも動画や文章など色々ある中で、なぜ写真は無くならないのでしょうか?絵よりお手軽だとか動画よりデータ量が小さくて扱いやすいとか、細かいことを考えれば色々あるかもしれませんが、僕が思う写真の最大の特徴は、現実に存在したある一瞬の様子を切り取って、好きなだけ長い時間目に焼き付けることができるという点です。これは絶えず流れていく時間の中で普通に経験した物事の記憶や動画では不可能なことであり、より強く印象に残るはずです。アインシュタインがペロッと舌を出したのを動画に撮っても、アインシュタインの名前を聞いて皆がすぐに思い浮かべるほど有名なものにはならなかったでしょう。
<写真の分類>
身の回りの写真を、左端を「記録性」、右端を「創造性」とする一つの軸の上にプロットすることで考えてみたいと思います。記録性の高い写真は実際にある/あった物事を客観的に映し伝えるものであり、創造性の高い写真は撮り手が見せたいものを見せたいように映すものです。たとえば図鑑や論文に載っている写真は、左端にあります。抽象写真(こういう時にサラッと具体的な写真家の名前でも出てくるとカッコいいと思うんですが残念ながら僕は知りません)は右端に来るでしょう。報道写真は左寄り、猫の写真は真ん中〜右寄りくらいでしょうか。
もう2年も前のことになりますが、ドイツのあるアーティストが、AIにより作成した画像を世界的な写真コンテスト、ソニー・ワールド・フォトグラフィー・アワードに応募し最優秀作品に選ばれるという出来事がありました。作者は後に作品がAIによって作られたものであることを明かし、受賞を辞退しました。コンテストを試し、写真の未来について議論を起こすために応募したのだといいます。「創造性」の高い写真についてAIを活用することは写真作品の新たな可能性として興味深く思う一方、報道写真など「記録性」の高い写真で同じことをすれば、それはただのフェイクであり、場合によっては取り締まられるべきものです。難しいのは軸の真ん中あたりに位置する写真です。インスタ映えの写真は軸の真ん中あたりに来る気がしますが、AIに架空のインスタ映えスポットを描かせてアップするのはどうでしょう…。AIが描いたネコの写真展(というかイラスト展?)も悪くないか…。
<「いい写真」って何?>
どんな写真が「いい写真」と言われるのか、当然一言で説明できるようなことではないのでしょうが、これも先ほど述べた軸のどこに位置する写真なのかによって変わってくるはずです。写真は被写体と撮り手の貢献によって出来上がりますが、例えば「創造性」の極致にある抽象写真は、撮り手が作品の隅から隅までコントロールすることが可能であり、したがってそのコントロールの仕方やその作品によって撮り手が何を伝えたいか、が写真の良し悪しを決めることになります。一方で少なからず「記録」の意味合いを持つ写真については、撮り手が被写体の全てをコントロールすることは不可能であり、被写体自体の「良さ」が写真の「良さ」に関わってきます。この被写体の貢献度は「記録性」とともに上がっていくように思います。アメリカの著名な報道写真賞であるピュリッツァー賞の受賞作品を見ても、記録としての被写体の深刻さを撮り手の技術が引き立てているような印象を受けます。最後に無理やりゴルフ部に話を戻しましょう。リーグ戦の写真はどちらかといえば「記録性」の高い写真に分類されると僕は考えています。リーグ戦でいい写真が撮れるかどうかは、被写体であるプレーヤーによるところが大きいのです。入部して以来の2年間、先輩方や同期がリーグ戦で戦う姿をカメラで追いかけ、この春やっと被写体側に立つことができましたが、自分がファインダー越しに見てきた先輩方の姿には到底及んでいません。卒部まであと1年半、この差を少しでも縮められるように努力を重ねていきます。
最後に、興味の追究と社会貢献のバランスが求められる理学部の学生として、この文章のような独りよがりの人間になり過ぎないよう、自戒の念を込めてこのブログを締めたいと思います。もし伊藤以外にここまで読んでくださる方がいらっしゃったのなら、ありがとうございました。(もちろん伊藤もありがとう。)
続いては、歯に絹着せぬ物言いと魅力的なスイングでお馴染み、大場に引き継ぎたいと思います。